前提知識
フーリエ変換
詳細は フーリエ変換 を参照。
周期関数に限らず、任意の関数 $f(t)$ は、正弦波($A \sin{\omega t}$ や $A \cos{\omega t}$。$A$, $\omega$ は定数)の和で表現できる(数学的な証明はここでは行わない)。
$t$ を時間 [s] とすれば
- $\omega$ は波の角周波数 [rad/s](周波数 $f$ [Hz] との関係は $\omega = 2\pi f$)
- $A$ は波の振幅
にあたる。
フーリエ変換 = 関数 $f(t)$ を様々な周波数 $\omega$ の正弦波に分解する変換。各周波数の波がそれぞれどの程度の強さ(= 振幅 $A$)で混ざり合っているのかを求められる
【公式】フーリエ変換
フーリエ変換:
\[F(\omega) = \displaystyle \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} \,dt \tag{1}\]フーリエ逆変換:
\[f(t) = \displaystyle \cfrac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} \,d\omega \tag{2}\]
【例】
元関数:

フーリエ変換:

フーリエ逆変換:

離散フーリエ変換(DFT)
DFT = Discrete Fourier Transform
コンピュータで扱うデータとしての波は連続値ではなく離散値であり、無限個の処理はできない。
→ 関数 $f(t)$ を、あらゆる(= 無限個の)周波数の波ではなく、有限個の異なる周波数 $\omega_i\,(i = 1, \cdots , N)$ の波に分解する。
- データサンプルの計測時間長 $T$
- サンプル総数 $N$
- 各サンプルの計測時刻 $t_n$、計測値 $f_n$($n = 0, \cdots, N-1$)
- サンプルは等間隔に取得:$t_n = n \Delta t$
に対して、DFT における周波数分解能は
\[\Delta f = \cfrac{1}{T}\]また、時間間隔は
\[\Delta t = \cfrac{T}{N}\]で与えられる。
$f(t)$ の DFT は
\[F(\omega) = \displaystyle \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} \,dt = \displaystyle \sum_{n=0}^{N-1} f_n e^{-i \omega t_n} \Delta t = \displaystyle \cfrac{T}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f_n e^{-i \omega \frac{nT}{N}}\]強度を求めたい周波数も等間隔に取り、
\(\omega = k \Delta \omega = 2 \pi k \Delta f = \cfrac{2 \pi k}{T}\) \(k = 0, \cdots, N-1\)と置くと、
\[F_k = F(\omega) = F(2 \pi k \Delta f) = \displaystyle \cfrac{T}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f_n e^{-i \frac{2 \pi}{N} nk}\]各周波数の強度(スペクトル密度)は、これを計測時間長 $T$ で割って
\[\displaystyle \cfrac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} f_n e^{-i \frac{2 \pi}{N} nk}\]これは複素数であり、
- 実部:波の偶関数成分(cos)
- 虚部:波の奇関数成分(sin)
という対応になっている。この複素数の絶対値を取ることでスペクトル密度が得られる。
1つの $k$ についてフーリエ係数を計算するのに $N$ 回の和を取るので、全ての $k$ について係数を得るための計算量は $O(N^2)$。
高速フーリエ変換(FFT)
FFT = Fast Fourier Transform
基本的な考え方
前提として、$N$ は2の冪乗となるように決める。
$F_k$ の和の部分
\[c_k \equiv \displaystyle \sum_{n=0}^{N-1} f_n e^{-i \frac{2 \pi}{N} nk}\]を高速に求めたい。
和を添字の偶数・奇数で分解
和の各要素を添字の偶数・奇数で分けると、
\[\begin{eqnarray} c_k &=& \displaystyle \sum_{n=0}^{N-1} f_n e^{-i \frac{2 \pi}{N} nk} \\ &=& \displaystyle \sum_{n=0}^{N/2-1} f_{2n} e^{-i \frac{2 \pi}{N} 2nk} + \sum_{n=0}^{N/2-1} f_{2n+1} e^{-i \frac{2 \pi}{N} (2n+1)k} \\ &=& \displaystyle \sum_{n=0}^{N/2-1} f_{2n} e^{-i \frac{2 \pi}{N/2} nk} + e^{-i \frac{2 \pi}{N} k} \sum_{n=0}^{N/2-1} f_{2n+1} e^{-i \frac{2 \pi}{N/2} nk} \end{eqnarray}\]- 複素数空間の回転単位(回転子)$w_N \equiv e^{-i \frac{2 \pi}{N}}$
- 偶数添字・奇数添字成分 $f_n^{\rm e} \equiv f_{2n},\,\, f_n^{\rm o} \equiv f_{2n+1}$
と置くと、
\[\begin{eqnarray} c_k &=& \displaystyle \sum_{n=0}^{N-1} f_n w_N^{kn} \\ &=& \displaystyle \sum_{n=0}^{N/2-1} f_n^{\rm e} w_{N/2}^{nk} + w_{N}^{k} \sum_{n=0}^{N/2-1} f_n^{\rm o} w_{N/2}^{nk} \end{eqnarray}\]最後の式を見ると、
- 第1項:要素数 $N/2$ の DFT
- 第2項:要素数 $N/2$ の DFT に $w_N^k$ をかけたもの
となっている。
即ち、要素数 $N$ の DFT は、要素数 $N/2$ の DFT 2つに複素数 $w_N^k$ を掛けて和をとる処理に分解できる。
分解された2つの DFT はそれぞれ計算量
\[O\left(\left(\frac{N}{2}\right)^2\right) = O\left(\frac{N^2}{4}\right)\]となり、元の DFT の 1/4。
分かれた2つの DFT も再帰的に要素数半分の DFT の和に分解していくことができ、最終的には要素数1の DFT(要素の値をそのまま返却するだけ)になる。
$k \lt N/2$ かどうかで分けて考える
任意の $k$ について、
\[\begin{eqnarray} w_N^{k+N/2} &=& e^{-i\frac{2 \pi}{N}(k + N/2)} = e^{-i\frac{2 \pi}{N}k}e^{-i\pi} = - w_N^k \\ w_{N/2}^{k+N/2} &=& e^{-i\frac{2 \pi}{N/2}(k + N/2)} = e^{-i\frac{2 \pi}{N/2}k}e^{-i2\pi} = w_{N/2}^k \end{eqnarray}\]であるから、$k = 1, \cdots , \frac{N}{2}$ に対して
\[\begin{eqnarray} c_k &=& \displaystyle \sum_{n=0}^{N/2-1} f_n^{\rm e} w_{N/2}^{nk} + w_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} f_n^{\rm o} w_{N/2}^{nk} \\ c_{k+N/2} &=& \displaystyle \sum_{n=0}^{N/2-1} f_n^{\rm e} w_{N/2}^{nk} - w_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} f_n^{\rm o} w_{N/2}^{nk} \end{eqnarray}\]この式より、$c_k$ と $c_{k+N/2}$ の計算には同じ DFT、$w_N^k$ の値が使えることが分かる。
即ち、$k = 1, \cdots , N$ のそれぞれに対して個別に DFT 2つと $w_N^k$ の計算が必要だったところを半分にできる。
【NOTE】
2つの DFT($c_k$, $c_{k+N/2}$)を求める問題が、要素数半分の別の2つの DFT を求める問題に変換されている。
再計算を避けるための工夫
各 $k$ の DFT を個別に分解・計算すると、別の $k$ のときに一度計算したものを再計算してしまうことになり非効率。
例として、要素数8のデータサンプルの DFT を考える。
各 $k$ に対応する DFT を要素数1の DFT(= そのまま要素を返すだけ)になるまで分解した結果を以下の図に示す。
- 矢印は実際に計算するときの流れ
- 2本の矢印の合流点で、一方に $w_N^k$ や $-w_N^k$ をかけて足す
- 矢印を逆にすれば、元の DFT が分解されていく過程になる
f_eやf_oeoなどは、添字の偶奇による DFT 分解の過程で作られた、元データの部分集合eは偶数添字、oは奇数添字を抽出したことを示す- 例えば
f_oeoはf = [f0, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7]- 奇数添字を抽出:
f_o = [f1, f3, f5, f7] - 偶数添字を抽出:
f_oe = [f1, f5] - 奇数添字を抽出:
f_oeo = [f5]

この図が FFT の計算フロー。図の形から、バタフライ演算 と呼ばれる。
この計算フローには
- いずれのステップにおいても、2つの DFT の結果から、後のステップで使う新しい2つの DFT を計算
- 一度使った DFT は他の計算で再利用されないので捨てても困らない
という特徴があるため、長さ $N$ の配列(初期値はデータサンプル $f_n$)をステップごとに書き換えていくことで、空間計算量を節約できる(別配列を作る必要がない)。
(TODO: 続き。最終的な時間計算量)
FFT の実装
関数
\(\begin{eqnarray}
f(t) = A_1 \sin{2 \pi f_1 t} + A_2 \sin{2 \pi f_2 t}
\\
A_1 = 1.0,\, f_1 = 1.0 \mathrm{[Hz]}
\\
A_2 = 0.2,\, f_2 = 2.5 \mathrm{[Hz]}
\end{eqnarray}\)
に対して、実装した FFT を適用してみる。
また、numpy の fft 関数の結果と誤差がないか比較する。

- いずれの実装も、numpy の fft 関数との誤差は極微小(正しく実装できていそう)
- $f(t)$ の定義通り、$f_1 = 1.0 \mathrm{[Hz]}$ と $f_1 = 2.5 \mathrm{[Hz]}$ のあたりにピークが観測される
- また、フーリエ変換で得られた振幅の比は定義した $A_1$ と $A_2$ の比($1.0:0.2 = 5:1$)にだいたい一致
計算速度の比較
実装した各手法と numpy.fft.fft の速度を比較してみる:

DFT が圧倒的に遅いので、除外してデータ数を増やしてみる:

- 愚直に和を取る離散フーリエ変換に比べて FFT が圧倒的に速い
- 同じ FFT の中でも、バタフライ演算に対応すればさらに大きく高速化(
fftVSfft_poor) - バタフライ演算対応版に比べても、numpy の
numpy.fft.fftが速すぎる。実装どうなってるの…?
| 今回実装した FFT | numpy.fft.fft |
|---|---|
 |
 |
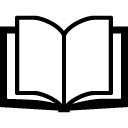 Technical Note - 高速フーリエ変換(FFT)
Technical Note - 高速フーリエ変換(FFT)